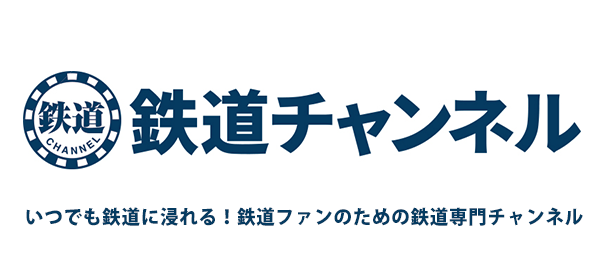三幸製菓のド定番「チーズアーモンド」って、いつもおうちにあったよね。いや、いまもおうちに、仕事場に、オフィスにあるよね。
あらためて、三幸製菓「チーズアーモンド」の歴史って長いなーと思うけど、実は40年も、昭和・平成・令和を通して親しまれてきたロングセラーなんだって!
ってことで、ここで、誰かに伝えたくなるような三幸製菓「チーズアーモンド」の歴史をチェックしていこう↓↓↓
【昭和】時代に先駆けた和洋折衷スナック

「おせんべいにチーズをのせる」という、当時としては異色の組み合わせ。
当時の代表による「米菓のイメージも徐々に変わっている。新しい発想による商品企画が大切」との考えのもと、三幸製菓は、1977 年に発売したミルクとサラダせんべいを組み合わせた当社の看板商品「雪の宿」をはじめとする多彩な商品を生み出してきた。
そんななか 1985年、ビール文化の普及や当時のウイスキーブームを背景として「お酒にも合う」商品の企画開発に着手。
口当たりの良い薄焼きせんべいに、クリーミーなチーズクリーム、そして香ばしいアーモンド。
和と洋の味わいが融合したこの商品は、おつまみとしてはもちろん、家庭の定番おやつとしても瞬く間に広まり、親しまれるようになった。
発売当初のパッケージには、どこか懐かしさを感じる昭和らしい意匠(デザイン)が光る。
【平成】多様なライフスタイルに対応 おつまみ化

平成に入り、日本国民の暮らしや消費の価値観は大きく変化していきた。
コンビニの全国展開や、家飲み・ひとり飲みといった個人化されたライフスタイルの広がりにより、手軽で満足感のあるひとくちスナックへのニーズが高まったのもこの時代。
そうした変化に応えるかたちで、チーズアーモンドの魅力をさらに磨くべく、味覚や機能性、嗜好の多様化に応えるラインナップを次々と開発・発売。
もうひとつ背景にあったのは、健康志向や素材へのこだわりといった高付加価値を求める意識の高まり、そして「限定品」や「変わり種」に惹かれる、遊び心ある消費傾向だった。
平成中期以降は、仕事終わりの「ちょっとしたごほうび」や、自分だけの時間を大切にする「マイペースな楽しみ方」が広がり、チーズアーモンドのような「なじみのある安心感」と「ちょっとした新しさ」を兼ね備えたお菓子が、多くのお客様に選ばれるようになっていきた。
おつまみとして構想された原点を大切にしながら、時代ごとの食文化や気分に寄り添い、柔軟に姿を変えてきたのが、平成期のチーズアーモンドだった。
【令和】体験・多様性・共創の時代へ

令和に入り、チーズアーモンドはこれまで以上に自由でユニークな発想で展開されるようになった。
これまでの定番のかたちを一度見つめ直し、素材の組み合わせそのものに新しいアプローチを試みている。
また、フレーバーをユーザーの投票で決定する参加型企画や、チーズアーモンドの世界観を体感できる期間限定のポップアップバル「CHEESE AND」の開催など、ブランドとユーザーがいっしょに遊べる仕かけづくりにも力を入れている。
こうした挑戦を続ける背景には、令和の時代ならではの社会の変化ともいえる、嗜好の多様化、SNS を通じた共感や話題性、選ぶ・関わる・体験すること自体を楽しむ消費行動がある。
昭和の時代に「おつまみとしても楽しめる」発想から生まれたチーズアーモンドは、いま、形や枠にとらわれず、もっと自由に、身近に、遊べる存在として広がりつつある。
変わらないおいしさを守りながらも、時代に合わせて姿を変えていく。それが、これからのチーズアーモンドのあり方―――。
チーズアーモンド担当プランナーの想い

「チーズアーモンドは、日常の中のちょっとした驚きや楽しさを通じて少しでもワクワクしていただけたらという思いで、さまざまな商品開発や取り組みをおこなっています。
ただ過去にはワクワクが過ぎてしまうことも多く、中でも 2020 年のハロウィンの時期に発売した「チーズアーモンドロシアンルーレット」は、通常のチーズアーモンドの中に激辛味が混ざっているという商品で、パッケージデザインもおどろおどろしく仕上げたのですが、あまりにも怖すぎて売り場で浮いてしまい全く売れませんでした。。笑
ただ新しい商品を出す度にお客様から「もっといろんな味を食べてみたい!」とうれしいお声を多くいただき、それがチーズアーモンドチーム一同モチベーションになっています。
これからも一人でも多くの人に笑顔のきっかけ作りができたらと思っております。
三幸製菓株式会社では、「Make Wow Moments. つくろう、ワォ!と楽しくなる瞬間。」をコーポレートブランドスローガンとして掲げています。
“Wow”とは、ワクワクやウキウキ、驚き、そして弾けるような幸せ。私たち三幸製菓は、みなさまにそんな“Wow”をお届けし、幸せのシーンを演出する存在であり続けます」
https://www.sanko-seika.co.jp/company/slogan/