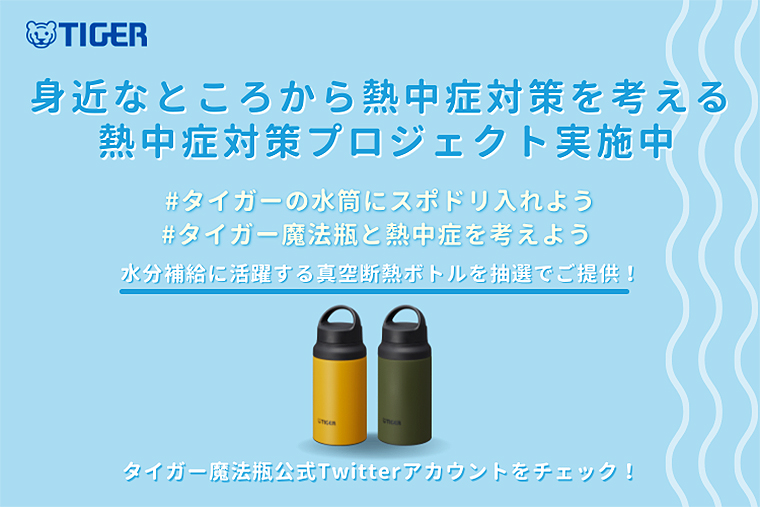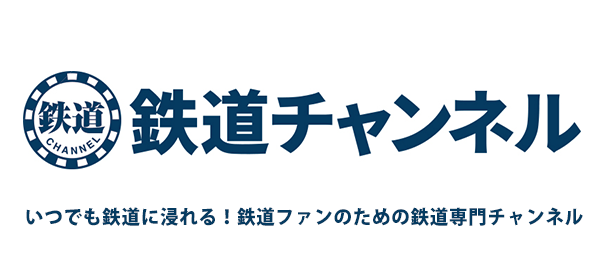ことし4月から、工学部 情報システム学科 で「自動運転専攻」が始動した埼玉工業大学は、既存の路線バス車両に同大学が開発する後付け自動運転AIシステムを搭載した いすゞエルガミオ(深谷市コミュニティバス「くるリン」)を毎日学生たちと進化させ、全国各地の路線バス事業者や自治体、各メーカーから注目を集めている。
埼玉県深谷市といえば、現一万円札の渋沢栄一の生まれ育った地。
埼玉工業大学開発 自動運転AIバス くるリン(深谷観光バス運行)は、深谷駅 北東に点在する渋沢栄一の生誕地やゆかりの地をめぐる定時定路線 北部シャトル+周遊便(総距離37km 所要時間112分)を自動運転レベル2で運行し、後退(バック運転)をともなう駐車場内切り返し以外はほぼ自動(運転手は監視のみ)で走っている。
社会実装されていく教材で地域も大学も未来を先取り

全国各地で運転士不足不足などの課題を抱える路線バス事業者や自治体地域交通担当者、各メーカー担当者は、「既存の路線バス車両に、埼玉工業大学の自動運転AIシステムを後付け(追加)で自動化できる」「自動運転バスの新車を購入するよりも現実的」と注目している。
いっぽう深谷市としては、地元の大学が開発した自動運転AIシステムで、地域交通を担う地元の深谷観光バスの車両を自動化でき、地域住民・市民がいちはやく自動運転バスの近未来を体感できるというメリットも生む。
さらに埼玉工業大学では、こうした“社会実装されていく教材”を、学生たちが日々進化させていき、地域の安全・快適な移動を実現させていくという使命感と楽しさを共有している。
―――こうした地域の社会課題解決と大学教育が両輪となってすすむバスの“心臓部”である埼玉工業大学 自動運転AIシステムは、いま想わぬところから注目を集めているという。
それが、国内最大規模の公共交通機関

それが、国内最大規模の公共交通機関。
“国内最大”ということもあり、既存の路線バス車両数も多く、バス車両メーカーも複数、年式やサイズもいろいろあり、「すべてを新車の自動運転バスに置き換えるよりも、既存路線バス車両を自動化していく」という道が現実的とみているらしい。
そしてこうした自動化に向けて埼玉工業大学に注目する担当者たちは、“後付け自動化”にもうひとつのメリットを期待している。
それが、すぐバラせる追加できる 柔軟性・汎用性・冗長性

たとえば深谷市 自動運転AIバス くるリン(深谷観光バス運行)は、埼玉工業大学 副学長(産学連携担当)自動運転技術開発センター長 渡部大志 教授が率いる自動運転AIシステム開発チームが毎日の運行を見守りながら、プログラムやアルゴリズムをアップデートさせ、ときには LiDAR(光による検知と測距)や GNSS (全球測位衛星システム) 、ビジュアルオドメトリなどのデバイスも設置・設定・更新している。
“後付け自動運転AIシステム”ならではの、「すぐに追加できる、バラせる、組み直せる」という柔軟性・汎用性・冗長性に、各地の自動化担当者は期待を寄せている。
会社の垣根を越えたサスティナブルな車両のやりくりも期待

自動車関係者は、こんなメリットも教えてくれた。
「路線バス車両は、地方のバス事業者などへバス車両を譲渡することもよくあり、もとの状態に戻して引き渡すといったケースも多い。今後は自動化されたバスを譲渡することもあると想われるが、こうした“後付け”の柔軟性によって、会社の垣根を越えたサスティナブルな車両のやりくりも期待できる」
ベテランの運転手が操作しているような“人間らしさ”

8月中旬に乗ったときも、2か月前の「自動運転 レベル4 区間で連続無介入走行100回達成」(6月)時からさらにアップデートを重ね、右左折時の安全性・快適性、信号有無を問わず交差点の進入・通過も、確実に向上している。
運転手が「ほぼ週ごとに誰でもわかるぐらいに快適性・安全性が進化している。お客さんも気づいている」というぐらいだから、その“成長”を実感する。
衝撃的だったのは、信号あり交差点の左折時。いつもどおりすべて自動で交差点に進入し、左折の途中、前方に停車中の赤信号待ち縦列停車先頭者がすこし停止位置より前に出ていたのを自動運転AIバスが感知し、すぐさまハンドルを“増し切り”して回避する。
このあたりは、ベテランの運転手が操作しているような“人間らしさ”だ。
学生と地域にとってもいいシナジー

「埼玉工業大学が他の大学と違うのは、文系や理系など関係なく、自動運転というトレンドにかかわって、社会実装されて地域の人たちといっしょにつくっていく、共感する、アップデートしていくという“現場”で学べるところ。
LiDAR(光による検知と測距)や GNSS (全球測位衛星システム) 、ビジュアルオドメトリなどのデバイス設置・設定から、自動運転AIシステムのアップデート、そしてシステム多重系化まで、学生たちがメーカーや運営会社、自治体といっしょにつくりあげていく。
地域の人たちの声を聞き、自動運転が社会実装されて、地域の人たちによろこんでもらえるまで、自分たちの学び・専攻が活かされるところが、学生と地域にとってもいいシナジーを生んでいます」(埼玉工業大学 副学長 自動運転技術開発センター長 渡部大志 教授)