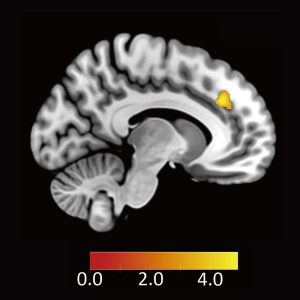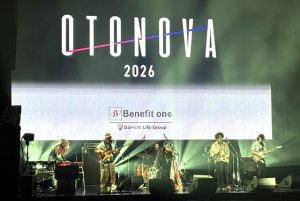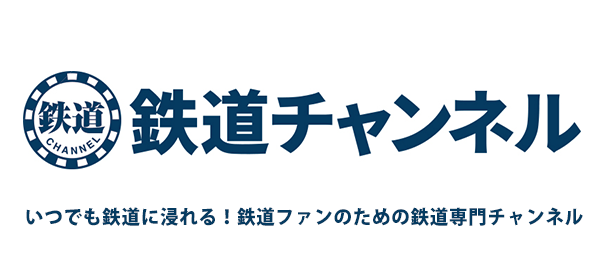大分県は2025年11月12日、東京都千代田区にある大分県公式アンテナショップ「坐来大分(ざらいおおいた)」 にて、「日本一のおんせん県おおいた味力(みりょく)も満載 おおいた自慢の郷土料理 試食会」と銘打ち魅力発信イベントを開催した。
“おんせん県おおいた”として知られる大分県、湧出量・源泉数ともに全国1位は伊達じゃない。その魅力に惹かれる最近では国内外の旅行者も多いが、温泉が有名過ぎるがゆえの悩みもある。大分県企画振興部の田吹美紀広報広聴課長は、「『由布院と別府は知ってるけど温泉以外には何があるの?』『県庁所在地は別府市じゃないの?』と聞かれることもあるぐらいです」と語る。もっと大分のことを知ってほしい、実際に足を運んでほしいという想いから、こうしたイベントを通じて情報を発信している。
大分県といえば有名なのはキリシタン大名・大友宗麟だ。その庇護下に置かれていたことから、かつては南蛮貿易により豊かな国際都市として栄えた。また幕末まで8藩7領という小藩分立政策が敷かれていたこともあり、県内各地で独特な文化が育まれ、地場産業が栄えた。
食においても同じことが言える。古くは「豊の国」と呼ばれた豊かな食文化でも知られ、文化庁が認定する「100年フード」には、“戸次(へつぎ)のほうちょう”や“佐伯(さいき)ごまだし”など4件が選ばれているほか、“とり天”や“日田やきそば”といった比較的新しい食文化も発展している。
今回の試食会は、こうした伝統と新興の食文化が融合する“おおいた自慢の郷土料理”の魅力を紹介するものだが、大分の県産品を使用し、坐来の櫻井料理長による現代風のアレンジが加えられた。
提供された主な郷土料理
きらすまめし(臼杵市)

臼杵藩の財政難による倹約令の中で生まれた節約料理。刺身の切れ端に、安価なおからをまぶして作られた。名前は臼杵地方の方言で「おから(きらず)」を「まぶす(まめす)」ことに由来している。
とはいえ現代は倹約令が敷かれているわけでもない。試食会では栄養バランスや彩りを考えてアレンジされ、カッテージチーズを加えたものが提供された。
鮑腸/ほうちょう(大分市戸次)

大分市戸次地区に伝わる郷土料理で、「100年フード」にも登録されている。鮑の腸のように小麦粉を細く伸ばして茹でた麺を、薬味入りのつけ汁で味わう伝統の手延べ料理。鮑の好きな大友宗麟に献上されたことが由来。
試食会ではそんな「ほうちょう」をパスタ風にアレンジし、贅沢に鮑の肝を使用。"おおイタリアン" とでも言うべきだろうか。
多彩な「寿司」

・ひたん寿司(日田市)
地元の川魚や山の幸を使い、柚子やかぼすの香りをきかせた上品な味わいが特徴。青い高菜で巻いた。写真では分からないが、埋め込まれた長芋が食感のアクセントになっている。
・とっきん寿司(日田市)
「頭巾(とっきん)」という言葉に由来し、三角にとがった形が頭巾に似ていることから名づけられたと言われている。五目ちらしで作るのが主流だが、今回は宇佐勝ちえびや宇佐の味一ねぎを使用した。
・蕎麦寿司(豊後高田市)
手打ちそば認定店が多く存在する「蕎麦処」として知られる豊後高田市で、酢飯の代わりに蕎麦を使った巻き寿司として楽しまれている。今回は合鴨農法で使われている鴨と白葱を合わせた。
・物相(もっそう)寿司(中津市)
米が貴重だった時代に、皆が平等に食べられるよう定量で切り分けるために「物相型」を用いたことに由来するとされる。今回は古代米や太刀魚を使用している。
やせうま(由布市)

由布市発祥の郷土菓子。小麦粉を薄くのばして茹で、きなこや砂糖をまぶした素朴な甘味。現在もお盆行事や家庭で親しまれている。 その由来は平安時代、貴族の若君が乳母の「八瀬(やせ)」に、「八瀬、うま(幼児の食べ物をさす言葉)」とせがんで作らせた料理であることとされる。そこにピオーネや無花果、梅蜜煮にアイスも添えて、アラモード仕立てに。
イベントでは、これらの郷土料理の試食のほか、おんせん県おおいたの観光情報や今夏稼働したホーバークラフトの紹介などが行われた。
羽田から大分空港まで1時間半というから、実は都民にとっても意外とタイパのいい旅行先である。大分の多様な食の魅力をぜひ現地で味わってほしい。
記事:一橋正浩