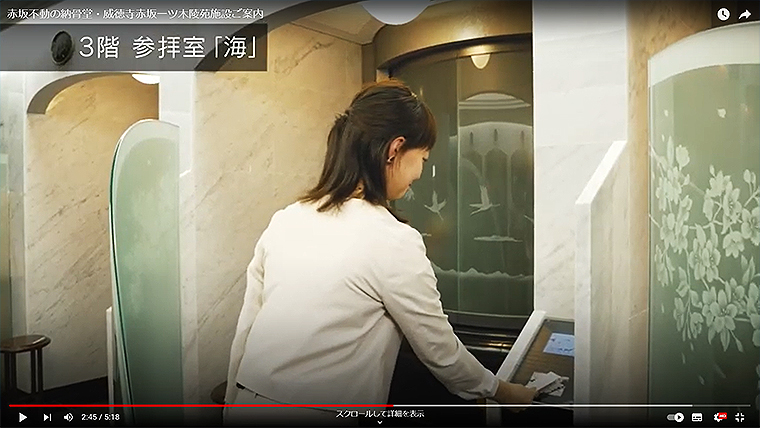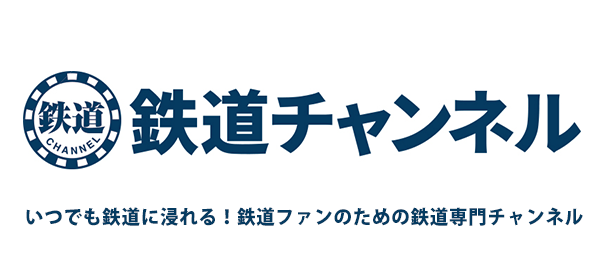おだやかな風ふく田畑に囲まれたキャンパスからは、遠くに赤城山・榛名山をのぞみ、しかも最寄り駅からは上野東京ライン・湘南新宿ラインで東京・新宿・渋谷まで1時間20分という好立地に、人間社会学部 情報社会学科 心理学科、工学部 機械工学科 生命環境化学科 情報システム学科の 2学部 5学科を展開する学び場 ――― 埼玉工業大学。
文系・理系の枠を超えた学び、自然に恵まれたひとつのキャンパスで4年間を過ごせて、講義・研究もスポーツも食事もサークルもぜんぶそろって、しかも東京・新宿・渋谷までも電車ですぐ行けるという“距離感”もいいってことで、全国から学生が集まる埼玉工業大学を深く知るならば、夏のオープンキャンパス!
7/13 7/26 8/9 8/23 開催
埼玉工業大学 2025 オープンキャンパスは、7/13 7/26 8/9 8/23 開催。
内容は、研究室公開、体験実習、模擬授業、キャンパスツアー、入試説明会、奨学金説明会、個別相談と、模擬面接体験(要予約 7/13 7/26 8/9 8/23)、面接試験対策講座(7/13 7/26 8/9 8/23)、教務課説明会(単位や学生サポートなど 7/13 8/9)、就職説明会(6/8 7/26 8/9)。
もうひとつの楽しみは、無料キャンパスランチ体験(11:30~13:30)。
埼玉工業大学を見学する合間に、食堂でランチ体験。3種類のメニューから好きなものを選んで、食べてみて!
メニューは毎回変わるから、楽しみ♪
―――ってことで、いま埼玉工業大学でアツい話題をピックアップ↓↓↓
情報システム学科 AI専攻に続き自動運転専攻を開設

埼玉工業大学といえば、学内に自動運転技術開発センターを設置するほどアツいのが、自動運転AIシステム開発。
ことしから、工学部 情報システム学科 に「自動運転専攻」も動き出し、まさに「自動運転といえば埼玉工業大学」と企業・自治体が注目するトレンドに。
そんな埼玉工業大学自動運転AIバスの最大の特長は、既存の路線バスに後付け自動運転A Iシステムを搭載し、全国各地の路線バスルートをレベル2で走り通せるところ。
この後付け自動運転AIシステムという独自性によって、全国の路線バス事業者が既存車両を自動化できることから、全国各地の自治体・路線バス事業者も注目し、実証実験への打診が相次いでいる。
現在は、埼玉工業大学と最寄り駅の高崎線 岡部駅などを結ぶスクールバス(画像↑↑↑)として活躍し、学生たちは毎日の通学で「自分の大学が開発するAIシステムの“いま”」を体感している。
ついには地元・深谷市の路線バスで社会実装

実際に、埼玉工業大学と最寄り駅の高崎線 岡部駅などを結ぶスクールバスは、全国各地の自治体・路線バス事業者などといっしょに実証実験とアップデートを重ね、ついには地元・深谷市の路線バスで新型自動運転バスを営業運転させるまでに実力を積み上げてきた。
これ(画像↑↑↑)が、埼玉工業大学 工学部 情報システム学科 自動運転専攻や、同大学 自動運転技術開発センターが手がけた、深谷市 コミュニティバス「くるリン」定時定路線 北部シャトル+周遊便(1回 総距離37km 所要時間112分)。
この くるリン、一般公道を営業運行する自動運転バスとしては、国内最長レベルの長距離で、しかも将来的には 自動運転レベル4(特定の条件下でシステムが完全に運転を担うレベルの自動運転)の実現をめざして、いまも営業運転を続けながらシステムをアップデートしていることから、全国から注目を集めている↓↓↓
https://www.sit.ac.jp/gakubu_in/kougaku/self-driving/
技術で社会を支えたい そんなあなたを待っています

埼玉工業大学 副学長 自動運転技術開発センター長 渡部大志 教授は、「未来のモビリティを、あなたの手で動かす。自分でつくったシステムが初めて動く瞬間の「ドキドキ」、その技術が社会のなかで実際に動く「感動」を体感してほしい」と。
「地域の方々からの「ありがとう」が、次の挑戦への原動力になりますし、埼玉工業大学の全学科が就職にも強いのが特長です。
埼玉工業大学 工学部 情報システム学科 自動運転専攻は、成長産業であるモビリティ・AI・IT分野へ幅広く進めます。
また、AI・IT専攻と共通カリキュラムが多く、将来の進路変更にも柔軟に対応できるのも、埼玉工業大学ならではです。
技術で社会を支えたい。そんなあなたを待っています」(渡部大志 教授)
環境物質化学研究室 クリーンエネルギー技術開発センターの最新技術も注目

こっちもすごい↓↓↓
埼玉工業大学 工学部 生命環境化学科 環境物質化学研究室 兼クリーンエネルギー技術開発センター長 本郷照久教授の研究チームは、陶器製の弁当容器から内装用タイル材をつくる技術を開発。
環境に優しい技術により、食後に残る釜めしの容器を資源として再利用できる未来が前進した。
この技術は、高温の熱処理や特殊な化学薬品などを使用する複雑な処理工程を必要とせず、環境に優しい技術を活用して、サーキュラー・エコノミー(循環経済)の時代に対応した環境負荷の低減に貢献。
本郷照久教授の研究室は、廃棄物問題などに着目し、物質化学をベースとした研究・開発により、廃棄物の有効活用を目指した問題解決に取り組んでいる。
廃棄物をゴミとして処分するのではなく、未利用の資源として活用する新規リサイクルシステムの開発により、SDGs時代に対応するサーキュラー・エコノミーに役立つ研究を推進している。
この研究成果は、「使用済み陶器製弁当容器からのジオポリマータイルの作製」というタイトルで、環境資源工学会が発行する学術雑誌「環境資源工学」(2025年第72巻第1号)に掲載された。
この研究では、全国的に知られる駅弁「峠の釜めし」の容器に着目し、再利用技術を開発しました。
廃棄物再利用技術開発と製品バリエーション拡充


「今回開発した技術は、シリカ(SiO2)やアルミナ(Al2O3)を含む様々な材料に応用可能です。
たとえば、廃棄される陶器類、耐火レンガ、瓦などにも広く適用ができる可能性があります。
また、この技術はさまざまな形態に固化できるため、タイルだけでなく、レンガ状の建材、ブロック、パネルなど多様な製品の製造にも応用が期待されます。
本研究室では、今後、これらの廃棄物の再利用技術の開発と、製品バリエーションの開発をめざして、さらなる研究を推進していきます」(本郷照久教授)
―――そんな最先端技術を学べる埼玉工業大学の詳細は、オープンキャンパスで体感してみて↓↓↓
https://www.sit.ac.jp/